北野 潤 特任准教授(きたの じゅん)

- 生態遺伝学研究室 北野研究室
- 1972年生まれ 京都大学大学院医学研究科博士課程修了、京都大学大学院生命科学研究科助手、フレッドハッチンソン癌研究所(アメリカ)博士研究員、東北大学大学院生命科学研究科助教。 2011年より現職。
受賞歴/2010年日本動物学会奨励賞、2010年日本進化学会研究奨励賞、2011年文部科学大臣若手科学者賞
趣味/研究
野生成物「イトヨ」の行動はどんな遺伝子で決まるのか?
トゲウオ科の魚「イトヨ」は、世界各地に生息し、生息地によって非常に形態や行動が違う。日本各地で、美しい水に住むふるさとの魚として親しまれており、生物学者にはニコラス・ティンバーゲンのイトヨの行動研究(ノーベル賞受賞)でも知られている。北野研究室は、このイトヨを研究対象に、フィールドワークから遺伝子解析、行動実験など多面的にアプローチ。様々な行動の違いや、種の分化は分子的にどのように起こるのか?そのしくみに迫っている。
- 野外でたくましく生きる生き物たち。その行動を決めている分子は何か?
- 北野特任准教授は医学部出身。脳内の化学物質によって様々に行動が変化する、その分子機構を研究をしていた。しかし研究しているうちに、野生生物に興味を持つようになった。
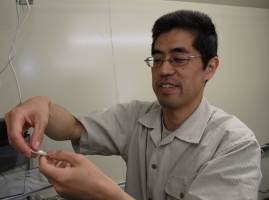 「野外の生き物には、攻撃的なもの、穏やかなもの、テリトリー意識の強いやつもいれば弱いやつもいる。そういう社会的な行動で成り立っている生き物に惹かれました。その行動の違いを生み出す分子機構を研究したいと思ったんです。7,8年前、そういう研究はあまりなかった。分子をやっている人は分子だけに興味があるし、逆に魚が好きだから魚の生態を研究しているというふうに、両方をやっている人はあまりいない。でも僕はそこに興味があったし、誰もやってないので、思い切って分野を変えたほうが楽しいかなと考えたんです。」
「野外の生き物には、攻撃的なもの、穏やかなもの、テリトリー意識の強いやつもいれば弱いやつもいる。そういう社会的な行動で成り立っている生き物に惹かれました。その行動の違いを生み出す分子機構を研究したいと思ったんです。7,8年前、そういう研究はあまりなかった。分子をやっている人は分子だけに興味があるし、逆に魚が好きだから魚の生態を研究しているというふうに、両方をやっている人はあまりいない。でも僕はそこに興味があったし、誰もやってないので、思い切って分野を変えたほうが楽しいかなと考えたんです。」- 文献をあたり、研究対象に適した野生生物を調べていくうちに、「イトヨ」を見つけた。初めて野生のイトヨを見たのは福井県大野市「イトヨの里」だった。
- 「見てみると、ちいちゃくて可愛い魚だし、実際その池で行動している魚が見える。それまではケージの中で飼われているマウスとかしか扱ってなかったのが、野外の池の中で繁殖したり、けんかしたり、食べ物を探したりしている魚を見たわけです。これがどういうホルモンや遺伝子によって制御されているのか?理解したいと強く思いました。」
- 研究内容紹介「野生生物の形態や行動の多様化は どんな遺伝子で決まるのか?」
- 自然環境を再現するのは難しい!
- 野外環境を再現する行動実験はなかなか難しい。苦労話として、アメリカでの実験の話が出てきた。
- 「湖の濁りと、天敵がイトヨを捕まえる効率の関係を調べるため、水槽に天敵とイトヨを入れ、水の濁り度合いを変えて比較したかったんです。ワシントンのサケ・マス孵化場にプールを借りて、まず天敵の大型の魚を捕りに行き、思いのほかいっぱい捕れたのでそこで飼い始めました。次にイトヨを捕りに行ったら、なぜかほとんど捕れなくて。仕方ないからずうっと毎日毎日、天敵にエサをやりに行って。次の年の春になって、いよいよイトヨが捕れる、となったら、天敵の魚の繁殖が始まって、夜明けごろになるとジャンプする。ある日行ったら水槽からほとんど飛び出して、個体数が減って。(笑)濁りをつくる実験も論文で読んだ粘土をプールに放り込んで溶かしたんですが、入れた直後は濁っても、次の日行ったら全部沈んでる。攪拌したら魚がびっくりするし、どうしたらいいんだ?!という話で。結局、水の濁りと捕食圧の関係は証明できなかったんです。」
- 津波による環境変化についても調査中
- 研究室では、東日本大震災で被害を受けた宮城県大槌町のイトヨも調査している。大槌町には美しい湧水があり、湧水が育んだ魚、イトヨを地域の人が大事に守っている。
- 「大槌町の人たちにとって、イトヨは町の誇り、湧水のシンボルとも言える存在だったのかもしれません。川にはイトヨ観察デッキがあるんですが、津波でひどく破壊され、がれきに埋もれました。こうした環境の変化がどんな影響を与えるのかも見ていきたい。日本海型と太平洋型が生息している日本で研究することはアドバンテージがあるし、日本の生き物で日本発の成果を出していくということは意識しています。大槌町のイトヨにしても、日本人が中心になって、町や人のことも理解しつつ、最先端の成果をあげていきたいです。」
- (田村佳子 インタビュー/高橋健太 動画作成 2011年)















