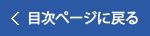荒木 弘之 教授(あらき ひろゆき)

- 微生物遺伝研究部門 荒木研究室
- 研究テーマ:真核生物染色体のDNA複製機構とその細胞周期による調節
研究は情熱と覚悟でできている
冷静な観察者の眼差しが印象的な荒木教授、教授の前では素をさらけだすしかない。 ちっぽけなごまかしは通用しない。
- 自分の弱さをみつめる強さ
- 厳しいことを言うようだけど、と前置きをして荒木教授は話し始めた。「どれだけ自分の全てを懸けられるかだよ。情熱と覚悟を持って研究をしてほしいよね」。これから研究者になりたい若者へ向けた教授の言葉に飾り気はない。研究に覚悟が必要、と率直に言う研究者がどれだけいるだろうか。研究への入り口、大学への進学時から「覚悟」ということを考え続けてきた荒木教授だから出てきた言葉だろう。
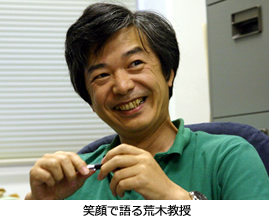 教授が大学生だった70年代は、理学部進学に多くの親が反対する時代だった。卒業後はどうするのか。何をやって食い扶持を稼ぐのか。「我々の頃は理学部に来るという時点でそれなりに覚悟しているんですよ」。荒木教授はさらりと言うが、その「覚悟」は他の学生より確かなものだった。その証拠に、後悔するほど学生時代はがむしゃらに勉強した。「今思えばもうちょっと遊んでおけばよかった」。1年生のときから教授に薦めてもらった専門書を読み漁り、知識の土台を築いた。4年生になってからは研究室に入り浸りの生活。午前2時より前に家に着いたことはなかった。
教授が大学生だった70年代は、理学部進学に多くの親が反対する時代だった。卒業後はどうするのか。何をやって食い扶持を稼ぐのか。「我々の頃は理学部に来るという時点でそれなりに覚悟しているんですよ」。荒木教授はさらりと言うが、その「覚悟」は他の学生より確かなものだった。その証拠に、後悔するほど学生時代はがむしゃらに勉強した。「今思えばもうちょっと遊んでおけばよかった」。1年生のときから教授に薦めてもらった専門書を読み漁り、知識の土台を築いた。4年生になってからは研究室に入り浸りの生活。午前2時より前に家に着いたことはなかった。- 「完璧な人なんていない。でも何がたりないのか、どこを鍛えればいいのか。それがわかればトレーニングをするだけだ」。結果が全ての研究の世界で生き残るために、荒木教授は必死になった。それは誰よりも自分の弱さを知っていたからなのかもしれない。
- 好きなことを続けるということ
 「生命の根源は遺伝にある」。何がしたいのか、何ができるのか、考え続けた荒木教授の興味はここに辿り着いた。以来、一貫してDNAの代謝に関わる研究に携わってきた。現在も酵母を用いてDNA の複製機構の解明に精力的に取り組んでいる。研究が気になりだすと寝られない。たったひとつの事が知りたくて数百キロ離れた研究室に駆けつけたこともある。体力の続く限り集中する。一方で、高校生の頃はわからなかった言葉の意味が、研究を始めてからわかった。「好きなことを仕事にすることは時につらい」。研究がうまく行かないときにも、それを紛らわすほど夢中になれるものがない。好きなことを追求できる喜びと逃げ場のないつらさはいつも背中合わせだ。それでも荒木教授は研究をやめたいと思ったことはない。それを支えるのは、結局のところ「どうしてだろう」という生き物へのシンプルな興味だ。
「生命の根源は遺伝にある」。何がしたいのか、何ができるのか、考え続けた荒木教授の興味はここに辿り着いた。以来、一貫してDNAの代謝に関わる研究に携わってきた。現在も酵母を用いてDNA の複製機構の解明に精力的に取り組んでいる。研究が気になりだすと寝られない。たったひとつの事が知りたくて数百キロ離れた研究室に駆けつけたこともある。体力の続く限り集中する。一方で、高校生の頃はわからなかった言葉の意味が、研究を始めてからわかった。「好きなことを仕事にすることは時につらい」。研究がうまく行かないときにも、それを紛らわすほど夢中になれるものがない。好きなことを追求できる喜びと逃げ場のないつらさはいつも背中合わせだ。それでも荒木教授は研究をやめたいと思ったことはない。それを支えるのは、結局のところ「どうしてだろう」という生き物へのシンプルな興味だ。- 今でも自分が研究に向いているかわからない。自分が歩んできた道が正しいのかどうかもわからない。そんな疑問を持ちつつも、ただ真っ直ぐに研究に取り組む。
- 自分の道を歩む研究者を育てたい
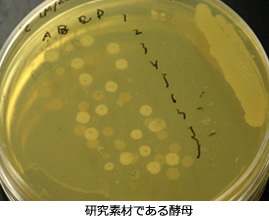 自分なりの試行錯誤を続けてきた荒木教授が、一人前の研究者になるために必須、と考えるのはディスカッションの力だ。人とディスカッションをすることで、自分の論理は正しいのか、どんな修正が必要なのかを明らかにできる。折に触れては研究室の学生や研究員に話しかけて議論を促す。「若い人は今やっている研究を将来的に続けるかどうかわからない。けれども、論理的な思考を身につければ、どこでも自分で実験を組み立てて研究を進められるようになる」。研究の厳しさを知っているからこそ、小手先ではない実力を育みたい。「生意気で結構。きちんとした根拠があれば、目上の人に反論することを躊躇しないで欲しい」。
自分なりの試行錯誤を続けてきた荒木教授が、一人前の研究者になるために必須、と考えるのはディスカッションの力だ。人とディスカッションをすることで、自分の論理は正しいのか、どんな修正が必要なのかを明らかにできる。折に触れては研究室の学生や研究員に話しかけて議論を促す。「若い人は今やっている研究を将来的に続けるかどうかわからない。けれども、論理的な思考を身につければ、どこでも自分で実験を組み立てて研究を進められるようになる」。研究の厳しさを知っているからこそ、小手先ではない実力を育みたい。「生意気で結構。きちんとした根拠があれば、目上の人に反論することを躊躇しないで欲しい」。- そしてもうひとつ。自立した研究者になるためには広い視野を持ち、なぜ自分の研究が重要なのかを説明できるようになることが必要だと最近頓に感じている。そのためにも、様々な価値観を持つ人と議論を重ねてほしいと願う。
- 研究者の姿はひとつではない。ひとりひとり違っていい。荒木教授の姿を間近にみられる研究室からは、しっかりと、自分の道を「情熱と覚悟」をもって歩む研究者が巣立っていく。
- (記事:株式会社リバネス 2006年インタビュー)