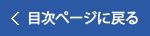平田 普三 准教授(ひらた ひろみ)

- 運動神経回路研究室 平田研究室
- 1973年生まれ 京都大学大学院理学研究科博士課程修了、京都大学ウイルス研究所博士研究員、ミシガン大学博士研究員、名古屋大学大学院理学研究科助手(のちに助教)。2010年より現職。受賞歴/2007年ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム・キャリア・デベロップメント・アウォード、2010年日本神経科学学会奨励賞 趣味/サッカー、フリスビー、ジャズ鑑賞、映画鑑賞
神経細胞のシナプスはどのように形成されるか
熱帯魚 「ゼブラフィッシュ」 は受精から17時間で動き始めるほど発生が速く、体が透明のため内部が観察できる美しいモデル生物だ。その後脳には 「マウスナー細胞」 という大きな神経細胞がある。平田准教授は、この細胞表面に存在するシナプス(信号伝達が行われる場所)について、遺伝的プログラムだけで形成されるわけではないことを発生過程の個体で見出した。神経活動による信号伝達が行われないと、シナプスは正常に形成されないのだ。この現象のメカニズムを分子のレベルで解明しようとしている平田准教授に聞いた。
研究内容紹介「脊椎動物の神経系や運動能力はどのように発達していくのか?」- 予想していない方向へ発展すると面白い
- これからの研究では、グリシン作動性シナプスの形成に必要な分子を同定して、その個々の機能を解析することで、神経活動による神経回路ネットワークの形成を理解していく。「関係する役者(分子)は細かいものまで入れるとたくさんいるでしょう。でも、看板役者、つまりキーになる分子がきっといるはずです。すごく重要で、そこに注目していれば全体が見えるような分子ですね。まだそれが誰なのか分からない。研究がどう展開するのか分からない。予想していない方向へ研究が発展するとますます面白くなりますね。」
- ゼブラフィッシュの変異体から、人の病気の解明へ
- もうひとつ、研究の方向性として、ゼブラフィッシュの変異体を用いた運動システム形成・発達の遺伝学的解析がある。どの遺伝子に変異があるかによって、運動時に硬直するもの、逃避運動をしないもの、運動スピードの遅いものなど、現れてくる異常も様々だ。こうした変異体の原因遺伝子を特定したら、ヒトの運動・行動異常の原因遺伝子と同じだったという場合がある。また、変異体の原因遺伝子が謎の新規遺伝子である場合もある。後者の場合、その新規遺伝子からヒトの未解明の遺伝性疾患が解明されることになる。「直接、人間の病気を研究しているのではないのですが、サカナの動きを通して、脊椎動物に共通する運動システムが理解できます。ヒトの疾患には運動障害をともなうものも多いので、将来的には人の病気やその治療に貢献したいと考えています。実際に、ゼブラフィッシュを用いて、運動障害の治療実験に成功した例もあります。」
- 漠然としたことをクリアに理解する、それがサイエンスの魅力
 「子供の顔って、両親に似てますよね。だから遺伝という現象は大昔からみんな漠然と分かってたんです。でもそれをちゃんと原理原則として説明できる人が昔はいなかった。19世紀にメンデルという人が登場して、それをメンデルの法則で説明したのです。私の研究においても、全体像は漠然としか分かっていません。この漠然としたものを科学の言葉で理解できる時が必ず来るんです。漠然としたことをクリアに理解すること、何の疑問をはさむ余地も無く全てを説明することこそ、サイエンスの魅力だと思います。逆に五里霧中の中、研究が停滞する時もありますが、こういう時はサイエンスの妄想を思いっきり膨らませることができる時でもあり、実は楽しい時でもあるのです。」
「子供の顔って、両親に似てますよね。だから遺伝という現象は大昔からみんな漠然と分かってたんです。でもそれをちゃんと原理原則として説明できる人が昔はいなかった。19世紀にメンデルという人が登場して、それをメンデルの法則で説明したのです。私の研究においても、全体像は漠然としか分かっていません。この漠然としたものを科学の言葉で理解できる時が必ず来るんです。漠然としたことをクリアに理解すること、何の疑問をはさむ余地も無く全てを説明することこそ、サイエンスの魅力だと思います。逆に五里霧中の中、研究が停滞する時もありますが、こういう時はサイエンスの妄想を思いっきり膨らませることができる時でもあり、実は楽しい時でもあるのです。」- 研究は楽しい。それが一番大事
- 大学院に入ってからサイエンスの面白さのとりこになった平田准教授。博士号を取得した時に指導教授に聞いた話は今も忘れない。「すごく間の抜けた質問ですが、『研究者はどうやったらうまくいきますか?』 と聞いたんです。そんな質問に答えがあるなら人生は容易すぎる・・・ (笑)。でも、先生は明確に答えてくださいました。『大事なことが2つある』 って。『まず、自分が健康であること』 。ハードワークとか情報力とか、そんな答えを予想していたので、意外でした。『次に、研究を楽しんでいること』 。これも必要条件だと思いました。『で、他には?』 って聞いても 『それだけだ』 って言うんです。『この二つさえあれば、研究者として、必ず道は開ける』 って断言したんですよ。それから10年経った今、先生の言葉がよく分かるようになりました。今後も研究を楽しんでやっていきたい。」
- (田村佳子 インタビュー/高橋健太 動画作成 2011年)