宮城島 進也 特任准教授(みやぎしま しんや)
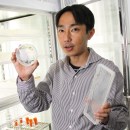
- 共生細胞進化研究室 宮城島研究室
- 1975年生まれ 東京大学大学院理学系研究科 博士後期課程修了、立教大学理学部博士研究員、ミシガン州立大学 博士研究員、理化学研究所独立主幹研究員。 2011年より現職。
受賞歴/2002年日本植物形態学会奨励賞、2004年日本植物学会 奨励賞、2005年 The Early Career Award,American Society of Plant Biologists、2010年日本植物形態学会平瀬賞
趣味/楽しく飲むこと
ミトコンドリアと葉緑体~異種細胞の共生と進化の謎
細胞内小器官である、ミトコンドリアと葉緑体。これらは、太古の昔には独立した生物だったが、10億年以上前に、真核細胞の中に取り込まれ、共生したと考えられている。異なった細胞がどのように統合され、ひとつの生物として生きていくようになったのか?ミトコンドリアと葉緑素の分裂に注目し、統合の機構がどのように進化してきたのかを、宮城島研究室は解き明かそうとしている。
- 2個の細胞が1個になる その過程が知りたい
 宮城島特任准教授がこのテーマを選んだ経緯を聞いてみた。
宮城島特任准教授がこのテーマを選んだ経緯を聞いてみた。- 「もともと、細胞の中にある物の形を見ることに興味があったんです。大学院のときに、葉緑体やミトコンドリアがどうやって動いたり増えたりするのかな、というのに単純に興味があって始めたことなんです。そしたら進化とかそういう問題が分かってきて。今、面白いと思っているのは、もともと別の生き物だったものが片方に取りこまれて、細胞の中に細胞がいるようなことになっている。2個の細胞から1個の細胞ができるっていう、その過程に興味があるんです。」
- こうした視点で研究している研究室は、かなり少ないという。
- 「ミトコンドリアの分裂の研究室はアメリカに4つくらいあるんですけど、対象は出芽酵母です。ミトコンドリアは進化とか多様化が進んでいて、生き物ごとに様子が違うんです。生き物全体にわたるような共通点がでてこない。何か見つかっても酵母にしかないということが多いです。生物の研究って、生き物が違えばいくらでも新しいことは出てくると思うんですけど、そんなことやっててもきりがない。遺伝子の機能を全部調べますって言っても、生き物が変われば遺伝子も違うし、進化してどんどん変わっているわけだから、全部の遺伝子の機能を見るなんて多分できないし、やっても意味が無い。そういうのではなく、原理という大きなものが見えるのが面白い。僕が知りたいのは、どうやってバクテリアが細胞に取り込まれて、一緒に増えるようになったかです。」
- 研究内容紹介「異なる二つの細胞がどのように共生し 新たな細胞として進化するのか?」
- 人工的に細胞内共生を作れないか?
- さらに野心的な目標として、「人工葉緑体」という言葉も飛び出した。
- 「理想は、細胞内共生を作ること。人工葉緑体とか人工制御ですね。シアノバクテリアとアメーバを混ぜて、食べさせて、分裂を操作できたら人工的に共生体を作ることができるかもしれません。現在、共生が起こりつつある生き物を見ると、取り込まれたバクテリアのほとんどの遺伝子はまだ宿主に取り上げられていないので、ほんのちょっといじるだけで一緒に増やす事ができるかな、と思うんです。そんなにたくさんのことが進化で一度に起きるわけないので、順番にどれかが起きて、チューンアップしてきたと思う。だから一番最初のイベントが知りたくて、それがわかれば作ることができるかもしれないと思っています。」
- 僕たちの細胞~真核細胞がどうやってできたかを知りたい
- 最後に、研究の意義について聞いた。
- 「僕の研究は、明らかに完全な基礎研究なので、何かの開発とか今すぐこれでエネルギー問題が解決するとかいうことに直結する研究ではないです。でもまず「物を知る」っていうことは人間のやりたいことです。例えば芸能鑑賞は生きるためには要らないのかもしれないけど、無きゃあ全然面白くない。人間がマシンとして、家畜として生きるのであれば要らないことかもしれないけど・・・。恐竜なんてたかだか何千万年前のものですけど、何十億年の間に、どうやって真核細胞ができてきたか?今の僕たちの細胞も含めて、どうやってできてきたのかを知ることはとても有意義なことだと思います。」
- (田村佳子 インタビュー/高橋健太 動画作成 2011年)















