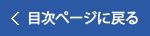鈴木 えみ子 准教授(すずき えみこ)

- 遺伝子回路研究室 (鈴木研究室)
- 研究テーマ:分子遺伝学および形態解析法を駆使した神経回路形成の分子・細胞メカニズム解析
確かな電子顕微鏡技術に裏打ちされた自然体の研究者
「いろいろやってみるけれど、結局は好きなことに収束する。それで良いのではないでしょうか」。電子顕微鏡室で鈴木准教授は穏やかに呟いた。
- 心惹かれる観察
- 電子顕微鏡を覗いていると、時が経つのを忘れる。鈴木准教授のベースは形態学にある。デスクの周りには大自然の風景や、植物の写真がところどころに飾られている。子どもの頃から身近な動植物をはじめ、自然に心惹かれていた。研究室に入って興味を持ったのは顕微鏡を使って観察する生き物の形だった。既に固定されているものの、切片から観察できる特徴的な生き物の形を目にすると心が落ち着いた。
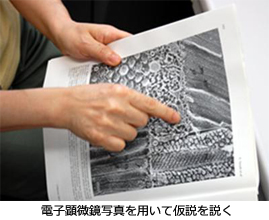 博士課程での研究を通して、形態学の可能性をはっきりと感じた。研究していたマウス肝細胞の顕微鏡観察から、「発生過程において、肝細胞は内皮細胞と出会うことによって分化する」ということが現象としてわかった。だが、目の前の写真が物語る仮説を証明する術を学生だった当時は持ち合わせていなかった。
博士課程での研究を通して、形態学の可能性をはっきりと感じた。研究していたマウス肝細胞の顕微鏡観察から、「発生過程において、肝細胞は内皮細胞と出会うことによって分化する」ということが現象としてわかった。だが、目の前の写真が物語る仮説を証明する術を学生だった当時は持ち合わせていなかった。- 現象を観察し、仮説を立ててから数年後、その仮説を裏付ける研究結果が生化学者によって発表された。それは「内皮細胞と肝細胞との間で、分泌因子による相互作用がある」というものだった。「やはり、そうだったか」。研究をしていて、最もうれしい瞬間だった。
- 研究の幅が広がる
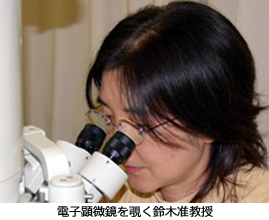 観察に主眼を置く形態学は、それだけで全てのことがわかるわけではない。けれども「見る」ということで、様々な仮説が生まれてくる。好きなことに夢中になるうちに、いつの間にか電子顕微鏡の技術を買われて共同研究の依頼が増えてきた。共同研究で実感したことは、ひとつの課題に対して、生化学、分子生物学、 遺伝学といろんな視点や手法でアプローチを行えば研究が進む。論文のトップオーサーではないかもしれないけれど、研究に貢献している感覚を持てるようになった。自分がリードする格好ではないことに、批判意見を浴びたこともある。けれども、「その時自分にできる最良のことをする」という誇りを持って続けてきた。
観察に主眼を置く形態学は、それだけで全てのことがわかるわけではない。けれども「見る」ということで、様々な仮説が生まれてくる。好きなことに夢中になるうちに、いつの間にか電子顕微鏡の技術を買われて共同研究の依頼が増えてきた。共同研究で実感したことは、ひとつの課題に対して、生化学、分子生物学、 遺伝学といろんな視点や手法でアプローチを行えば研究が進む。論文のトップオーサーではないかもしれないけれど、研究に貢献している感覚を持てるようになった。自分がリードする格好ではないことに、批判意見を浴びたこともある。けれども、「その時自分にできる最良のことをする」という誇りを持って続けてきた。- 神経発生を軸に様々な研究を他の研究者とともに進める中で、「自分が形態学で観察したことを基に立てた仮説を自ら証明したい」と考えるようになった時、遺伝研のポストに出会った。自ら研究室を主催する立場になり、分子生物学に精通した研究者を助教として招き、新たな挑戦を始めた。鈴木研究室に集うのは立場こそ違えども、みな大切な共同研究のパートナーだ。
- 自分のペースで続ける大切さ
- 静岡県三島市にある遺伝研での研究活動を行うために、東京にいる家族と離れて平日は単身赴任で過ごす。女性ということで研究に支障を感じたことはないが、子育て期間は研究ペースを落としたことも確かだ。子ども達が成長した今、充実した環境で研究に没頭する。形態学から得た仮説を証明するための挑戦の場所は獲得した。さらに遺伝研では、これまで無縁だった植物系の研究者からも共同研究の声がかかる。活躍の分野も広がっていく。「私と電子顕微鏡は一心同体」。確かな観察技術を軸に自分のペースで研究を継続する。
- (記事:株式会社リバネス 2007年インタビュー)