Career-Path Seminar
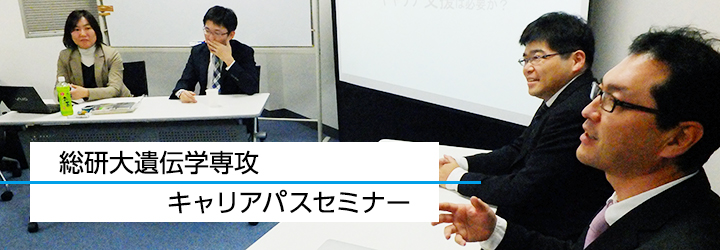
2014年1月、「総研大遺伝学専攻 キャリアパスセミナー」を開催しました。研究所では触れる機会の少ない、多様な職種のキャリアパスについて、その分野で活躍される総研大遺伝学専攻出身のOB・OGの皆さんにお話をうかがいました。講演者の皆さんのご経験やアドバイスは、学生の今後のキャリアパスを考える上での参考になりました。

![]()
筑波大学URA
(University Research Administrator) 【司会】
2003年修了。JST博士研究員、経営コンサルティング・ベンチャーキャピタルでの勤務を経て起業し、大学の研究者に対しさまざまな研究支援サービスを提供する。現在は、筑波大学の研究支援本部に所属し、学内だからこそできる研究者支援の形(研究戦略立案、国際連携、学内研究力分析など)を模索中。

![]()
大塚製薬株式会社 研究員
1996年修了。遺伝学研究所学術振興会特別研究員PD、UCSF Psychiatry Institute PD fellow(Rubenstein Lab.),Yale Univ. School of Med. Neurology, PD Associate (Vaccarino Lab.), Yale Univ. Child Study Center, Associate Research Scientist (faculty) を経て、2008年に大塚製薬入社。徳島研究所所属。

![]()
江崎特許事務所 弁理士
2004年修了。卒業時の所属研究室での博士研究員を経て、2006年大手特許事務所に転職。同時に弁理士試験の勉強を開始し、2008年に合格、翌年登録。2009年より現事務所に所属。

![]()
カールツァイス・マイクロスコピー株式会社
ライフサイエンス事業担当
2007年修了。ドイツ、ハイデルベルク大学およびゲッティンゲン大学で博士研究員として4年間勤務。2011年に帰国、カールツァイス・マイクロスコピー株式会社に入社。電子顕微鏡部門所属。
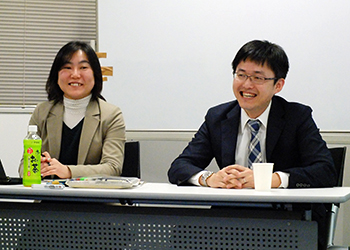
- 新道
- はじめに、どうして今のキャリアを選択することになったのか、どういうふうにしてそのキャリアに進んで行くことになったのか、プロセスをお話いただけますか?
- 兼崎
- 私が今やっている仕事は、電子顕微鏡のアプリケーション、つまり、研究者さんのやりたい研究を伺ったうえで、どういう顕微鏡が必要かということを提案することと、日本のライフサイエンス市場のマーケティングです。
研究者をしていたときに、研究活動を自分で組み立ててやっていくということよりも、むしろ、世界のいろんな研究者さんの新しい成果を読んで興奮していることの方が多く、自分で研究をやらなくても人生楽しめるのかな、と思っていました。自分の研究が一段落したこともあって、ライフサイエンスの世界には関われるけれど、リサーチではなく、常に最新の研究を知ることができる今の仕事を選びました。 - 虎山
- 僕は、仕事とプライベートを区別したかった、というのも研究を離れた動機の一つです。なぜ弁理士を選んだかといいますと、あまり組織に縛られたくなく、ある程度独立して自分で仕事をしたかったんです。その条件に合う職業を探して、研究に関係のある資格、弁理士を選びました。
- 大久保
- 私の場合はイェール大学にいたときに、研究費を得るために日米の製薬会社に企画書を出したら、複数の会社から「このアイデアにお金は出せないけれど、入社して研究をやってみないか」というオファーを受けたのがきっかけです。そのなかで、希望する分野の研究を継続できて、安定性もある大塚製薬に行くことにしました。現在は医薬品の研究開発をしています。
- 新道
- 私は、大学と社会をつなげる仕事がしたい、と思ったのがきっかけです。じつは、私がキャリアチェンジを考えていたころ、大学発ベンチャーが活発化し始めた時期なんです。そこで、大学の研究成果を社会に還元する方法の1つ、技術移転に興味をもち、ベンチャーキャピタルに転職しました。その後、起業、URAと変遷しているので、キャリアチェンジしているように思われるのですが、個人的には一貫して、大学の研究者を対象に研究支援サービスを提供し続けているつもりです。

- 新道
- 遺伝研で研究してよかったと思うことはなんですか?
- 虎山
- 弁理士の仕事は、お客さんの発明の中身を理解して、それを特許庁とお客さんとの間に立って、調整する役目なので、遺伝研にいたときに論文をたくさん読んだ経験は何物にも代えられないです。ポイントを絞って審査官とやりとりをするのですが、発明の本質を見抜く力は、遺伝研にいたころに養われたと思います。論文が書けるところまで、突き詰めて実験して研究した経験は修士までの学生では経験できないことだと思います。
- 兼崎
- 遺伝研は横の繋がりが密にあるので、いろんな研究分野の話を聞けました。この経験が、今とても役に立っています。当時の交流のおかげで、お客さんの研究が自分の専門分野以外でも、ある程度はわかります。
もうひとつは、副指導教官だった広海先生にすごく厳しくプレゼンテーションの指導をしていただいたのは、今本当に役に立っています。 - 大久保
- 遺伝研の学生はプレゼンテーションのレベルが高いですよ。周りのレベルが高いから引き上げられるんでしょうね。
- 兼崎
- そうですね。他の大学に比べてポスドク以上の研究者の比率がすごく高いので、スキルアップという点ではすごくよかったです。それに、海外で研究職に就いたり、企業へ就職したり、モデルケースをいっぱい見られて、将来のビジョンを持ちやすかったですね。
- 大久保
- 私の場合も、やはり鍛えられたことですね。ハイレベルな環境で研究をした経験があったので、就職活動でもハイレベルな仕事ができるところを目指そうと、緊張感をもって取り組めました。
ここのデメリットは民間にとっては無名であることなんです。意外と総研大って知られていないんですよ。ただ、「こんな組織があったんだ」と言われて、そこで充実した発表ができると、逆に好印象として記憶に残るんです。ですので、ぜひとも切磋琢磨していただきたいです。 - 新道
- 私も遺伝研時代に全力で研究をして最後までやりきれたことがあるから、たとえ初めてチャレンジすることであってもできるんじゃないかという自信に繋がった気がします。博士課程を最後までやったことで、すぐ結果が出なくても仕方がない、一回腹を決めたらしばらくはやってみようという覚悟がついたように思います。
- 新道
- 日本の大学を出た、新卒ではないドクター持ちの人材をとるような雰囲気は、業界としてあるんでしょうか?
- 兼崎
- ライフサイエンス業界で、とくに外資の企業では結構需要があると聞きます。研究職はあまりなくて、営業系かアプリケーションか、もしくはマーケティングですが。ライフサイエンスに必要な装置や試薬を扱う外資の企業は、ローカルの知識があって、ローカルの言語が喋れる人を探しているので。
- 虎山
- 特許業界では、事務所によっては積極的にポスドクを採用しているところもあります。正直なところ一番欲しいのは企業の知財部の出身者ですが、ポスドクも需要がないわけではないです。ただ、すごく少ないので、人脈が大切ですね。僕もそうだったんですが、狭い業界なので、面接のときに他の事務所を紹介してもらうことも結構あります。だから、とにかく顔を出しに行くということが重要ですね。
- 大久保
- 日本の製薬会社が全部そうだというわけではないんでしょうが、製薬会社は新卒採用がマジョリティーで、教授の推薦や大学のネームバリューは大きいです。アメリカでヘッドハンティングしている日本のある製薬会社の人事は「日本のポスドクはとらない」と言っていました。教授推薦がないと書類選考も通らないところもあるそうです。
ただ、ポスドクであろうと、学生であろうと、助教であろうと教授であろうと、こういうことが薬になるんじゃないか、こういうリサーチをしたらこの病気の薬ができるんじゃないかというアイデアを持ってきたら、いろんな不利な要素を全部ひっくり返すものになります。企業ですから、お金になることがわかっている人は採用します。 - 新道
- URAは、研究者を支援する仕事なので、博士のほうが喜ばれます。実際私たちの大学でもほぼみんなドクター持ちです。一方で、私が経験してきた金融関係や出版関係だと、まだ博士号を取った人が珍しいので、「変な人が来た」というふうに思われるのか「とりあえず一回面接に来なさい」と言われることがあると思います。ただ、募集が出ること自体が少ないので、見つけたら出すようにしていれば、興味がある業界ならチャンスがあると思います。

- 新道
- 最後にみなさんにメッセージをお願いします。
- 兼崎
- 10年先20年先のことのビジョンを持ちながら、今の仕事を続けてほしいです。でも、実際のところ10年後20年後って、なかなか想像できないんですよね。今想像してその通りのことをするというのは難しいと思う。だけど、考え続けないとやっぱりだめだと思うんです。常に未来というものをある程度意識したうえで生き続けることで、やっと個人個人にとって最良の道が開けてくるのかな、と思います。
- 虎山
- 今やっている研究を大事にしてほしいです。もちろん先のことを考えることも大事ですが、遺伝研の研究は本当に今しかできないことだと思いますので。自分のキャリアをどうするかというのは常にあるでしょう。でも、それはそれとして、遺伝研でそれなりにやっていれば、なんとでもなる、というのが僕のメッセージです。そのためには、今目の前にある実験ひとつひとつを大事にやってほしいです。
- 大久保
- 僕は海外に行ったほうがいいと思います。ポスドクを日本でやるのもいいですが、だめだった場合の保険というか、プランBを考えたら、むしろ積極的に経験を増やしておいたほうがいいです。向こうに行くと、研究者がだめなら企業に行くというのが、当たり前の選択としてあって、それに対して「ドロップアウト」と言っているのはハーバードの連中ぐらいなんです。そういう考え方が普通だというのを体感するためにも行った方がいいです。
- 新道
- 私もだいたいみなさんと同じなのですが、今、つまり研究している時間を大事にしてほしいということ、そして、面白そうだと思ったら躊躇せずいろんな経験をしてほしい、ということです。今日は、「非アカデミック分野のキャリアパス」についてが題材でしたが、研究の世界で頑張っている遺伝研卒業生はみな同じように思うのではないかな、と思います。いまはOGとして講演側にいますが、私のキャリアもまだまだ道半ばです。今をめいっぱい大事にしつつ、面白そうと感じた自分の心を素直に受け止め、経験を深めていけたらな、と思っています。お互い頑張りましょう!















