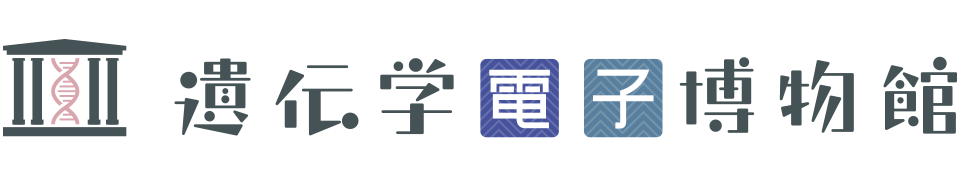遺伝学発展の歴史
遺伝学が学問として発展してきた歴史は(年表)に示した。遺伝学の歴史は細胞学の歴史と重なり、顕微鏡の発明により、生物体が細胞によって構成されていること、その細胞の中に核があり、その中に含まれる染色体に遺伝情報が蓄えられていることがしだいに明らかになっている。また、1865年Mendel(1865)が講演し、その翌年論文として発表した遺伝の法則が、遺伝学の歴史の中では最初の重要な位置を占めるが、実際にMendelの法則は発表された後35年間、誰にも気付かれずに過ぎ、1900年になってオランダのde Vries、ドイツのCorrens、オーストリアのTschermakという3名の植物学者によって、それぞれ別の材料を使って独立にMendelが発見したのと同じ遺伝の法則が再発見され、ここから遺伝学が始まったといっても過言ではない。
現象面での遺伝の法則は、動物植物のあらゆる遺伝現象にも適用され、育種や品種改良などの分野に広く利用されている。一方、細胞レベルでの研究は、染色体を中心としたゲノム解析や倍数体の研究へと進み、さらに細胞の体外培養法が開発されて、細胞の増殖、分化、老化をはじめ細胞がん化などの仕組みを調べる研究にも利用された。さらに細胞融合を用いた雑種細胞を形成させ、ヒト遺伝子のマッピングやモノクローン抗体の作成、さらにトランスジェニック動植物の作成などいわゆるバイオテクノロジーの応用分野へと発展した。
遺伝現象を支える遺伝子の物質的な面の研究は、それぞれの遺伝子がそれぞれの遺伝形質に対応するという従来の考え方から、遺伝子はそれぞれ一つずつの酵素に対応するという一遺伝子一酵素説がBeadleとTatum(1941)によって提唱され、遺伝現象の生化学的な研究の端緒となった。
また、遺伝子の化学的本体がDNA(またはRNA)であることは、1940年代に細菌の形質転換やファージの遺伝子組換えの実験から明らかになっていたが、1953年のWatsonとCrickのDNAの二重らせんモデルが提出されるに及んで、細胞分裂の際にDNAがもととまったく同じ分子を正確に複製する仕組みや、DNAのもっている遺伝情報がRNAを経てタンパク質に伝えられる仕組みがすべて明らかにされた。
さらにDNAの人工的な合成や制限酵素やリガーゼの発見によって、DNAを自由に切断したり結合したりする技術が開発されて、DNAの組換えができるようになり、DNAの塩基配列の決定法や、サザンブロット法、ノーザンブロット法およびウエスタンブロット法によるDNA断片の同定や、DNAからのRNAの転写活性、タンパク質生成(遺伝子発現)の研究など、分子レベルでの研究が格段に進んだ。
このような分子遺伝学の成果は各分野での応用面にも利用され、とくに医学の分野ではポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法を用いてDNAを増幅させ、これをDNA診断やDNA治療にも利用する試みがなされている。
遺伝形質の親から子へ、さらに孫への伝わり方の法則に始まった遺伝学が、このような遺伝現象をつかさどる遺伝子を荷う染色体を中心とした細胞遺伝学へと発展し、さらにその化学的本体であるDNAの構造やその働きが明らかにされた。そして、発生学や育種学、医学など生命を扱うあらゆる分野に広く浸透し、学術的な研究はもとより、社会的に関係のある応用面、利用面でも遺伝学との結びつきはますます深く密接になって行くと思われる。
「基礎遺伝学」(黒田行昭著:近代遺伝学の流れ)裳華房(1995)より転載